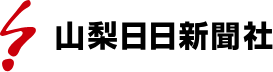フジマリモ4分の1に 山中湖 生息数、10年前と比べ

湖底の映像を見ながらの調査結果を確認する関係者=山中湖村役場
水温上昇影響 絶滅恐れも
山中湖に生息する山梨県の天然記念物「フジマリモ」の生息数が10年前に比べて4分の1以下に減少したことが26日、村教委と国立科学博物館の調査で分かった。湖水の温度上昇により、フジマリモの生息域を奪うシアノバクテリアが増加したことなどが要因とみられる。博物館の研究者は「このままでは絶滅の可能性があり、厳しい状況だ」と指摘。フジマリモの保護活動を展開している団体は「県全体で保護に取り組む必要がある」と訴えた。
フジマリモは淡水産の緑藻で、糸状の藻が絡み合い球体の形をつくる。1956年、山中小の児童が山中湖で球状の藻を発見し、マリモの一種と分かり「富士毬藻(フジマリモ)」と名付けられた。
生息数の減少は26日に村役場で開かれた会合で報告された。山中湖での調査は5年おきに実施していて、今回は昨年11月に湖北岸の「ママの森」と呼ばれる場所など3カ所でダイバーが水に潜り、湖底での生息数を目視で確認した。
調査した博物館の辻彰洋研究主幹によると、生息数は、2014年の調査時から半減した前回調査(19、20年)に比べ、さらに半分以下に減っていた。フジマリモが付着した石などの標本を採取できたが、球状のフジマリモは確認できなかったという。
辻研究主幹によると、フジマリモは近年の湖水温度の上昇により育ちにくくなっている。1980~2020年の40年間で、湖水の平均温度は2度ほど高くなっていて、比較的暑さに強い藻の一種シアノバクテリアが増加。藻の増加によりフジマリモが付着する岩の露出が減ったことが影響したとみている。
(2025年3月27日付 山梨日日新聞掲載)