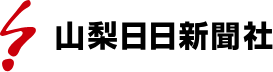雪の富士を極む 本社記者の国体同攀記
息つまる30メートルの突風 襲う寒気に鈍る感覚
御来光が真紅に燃えてクラストした白雪の霊峰に映え始めた午前5時温まった毛布をける、昨夜準備したカメラ2台を両肩に下着2枚にセーター、アノラックだけの軽装で夏路Cコースを選手団に先がけて報道班7社の16名の記者は山頂に向かった。
6合目で頂上への足をアイゼンでしっかりと結べば快晴、無風零下七度の寒さは毛糸の手袋をとおしてカメラをもつ手がしびれる、5合5勺で選手団の登はんを待つ、3名1パーテーに組んだ選手団の長蛇の列がちかづくと各社のカメラが一斉にシャッターをきる、7合目あたりからの氷雪の急斜面はアイゼンをつけないでは登はんを許さない選手団を見送って写したフィルムを本社へ急送のため下り6合5勺で記者に渡し再び選手団を追う。
きしむピッケル
7合目にかかった時は各社の記者は登行を中止し報道班は朝日、共同と3人だけになった、7合1勺の辺りよりBコース大沢口班を撮影するため右に進路をとった、富士第一の難場である、大沢口の斜面は一段と角度をまし吹きだした風速12、3メートルの突風は時を切って雪つぶての波をまき起してジクザクに登る選手団を襲う、頂上付近でパッと雪煙が上ると先頭から順次氷雪面にピッケルをつきさして伏せる、カメラを胸に抱きしめる耳がジーンとなる。
雪質に恵まれたこのコースはアイゼンが気持ちよくきき氷雪面もさほど硬くなくピッケルによるアイスカッテングもザイルも使わないで登はんがつづけられるつきさすピッケルがきしむ8合目辺りより単独で再度左に大沢口コースを離れCコース夏路の選手団に合流した、一番楽のこのコースの選手は雪山には不馴れの者が多いので慎重の一歩々々を踏んで登っていく、10時ごろよりの強風にあおられ8合目の小屋で中止した人々の姿がみうけられ、共同のカメラマンもここで断念したので報道班はついに2名となった。
疲労感忘れる景観
独りピッチをあける、道のすぐ左の小沢に真新しい10センチもある熊の足跡が下に向かってはっきりと残されて不気味だった、9合目を登る頃は空気の稀薄と強風のため呼吸の苦しさを感ずる、9合5勺で一寸一息つく。
ここからの展望は脚下に遙か太平洋が展開し近くに紅葉した青木ケ原の樹海を指呼の間にはさんで左に山中、右に河口の両湖が銀色に光っている、左は遠く東端より北へすでに初雪をいただいた秩父、金峰の山塊が連なり八ヶ岳が山頂をうす化粧してキ然と天空にそびえ、また真白い南アルプスの連峰が北アルプスと平行して富士の左の斜面より右に走っている、この眼下一望におさめる景観を楽しんだ一ときこそ、アルバイトの疲労を正に忘れさせるものがあった。
頂上に飜(ひるがえ)る山日旗
頂上の手前は先行者の足跡の氷雪がくずれてアイゼンがきかない、ピッケルを力に登る、ついに真白な大鳥居をくぐって雪中3776メートルの頂上に立つ、12時15分、ふぶき続ける風速20メートルの風は間断なくものすごく噴火口に渦巻きすべての生物の静止を許さない、また時には30メートルの突風に思わず這う、息がつまる、零下12度の寒さ、目がひりひり痛み頬が硬直して感覚が急速にうすらいでゆく、火口の対岸には山頂観測所が真白く氷雪に包まれて孤立し、薄ねずみ色に氷結した火口内は所々に真黒な大岩塊を露出させ不気味な様相を呈している。“山日旗”をしっかと結びつけたピッケルを力まかせに山頂につきさす、社旗が風にうなる、カメラのシャッターを切った感激が胸にこみあげる。
12時37分強風を背に大沢口の雪渓を下る、ふと振り返るとすでに富士山頂を西方に越えた初冬の斜陽が頂上を乱舞する雪煙に7色の大円虹を美しく描いていた。 【当時の紙面から】
(1949年11月6日付 山梨日日新聞掲載)